
ハラスメント防止に関連する研修特集
ハラスメント防止研修を、誰もが安心して働ける職場づくりの起点に。
ハラスメントは、企業の信頼と存続を左右する深刻な課題です。「悪意のない一言」でも、相手を傷つけることがある時代。組織全体が共通認識を持ち、正しい知識と対処力を身につけることが求められています。
本特集では、ノビテクが提供する【目的別】のハラスメント防止研修を紹介します。あわせて、ハラスメント対策の専門家・山藤祐子氏のコメントも掲載。現場で本当に必要とされる視点や対応方法をお伝えします。
目的別ガイド
- ハラスメントの基礎を学びたい:ハラスメント対策研修 ~防止のための基礎リテラシー~
- 管理職としての具体的対応を学びたい:セクハラ・パワハラ防止研修
- ハラスメントの再発防止をしたい:ハラスメント再発防止のためのオンラインコーチング
- カスタマーハラスメント対策を整えたい:カスタマーハラスメント対策研修
- 基礎知識と動向が知りたい:ハラスメント対策の基礎知識と最近の動向
ハラスメント防止に関連する研修
ハラスメント対策研修 ~防止のための基礎リテラシー~

ハラスメントリテラシーの向上を目的とした研修です。社員間の価値観の多様性を認め、ハラスメント基礎を学び、社内のハラスメントの防止に繋げます。
|
対象 |
役員・経営陣、管理職、若手・中堅、新入社員 |
|---|---|
|
目的 |
ハラスメントリテラシー向上、基礎知識習得 |
|
内容 |
・ハラスメント定義・発生原因 |
|
詳細 |
セクハラ・パワハラ防止研修

セクハラ(セクシュアル※ハラスメント=性的嫌がらせ)・パワハラ(パワーハラスメント=権力や立場を利用した嫌がらせ)の防止を目的とした研修です。管理職としての使命及び役割について認識を深めさせ、業務遂行上の知識及び技能の付与を図ります。
|
対象 |
管理職 |
|---|---|
|
目的 |
管理職としての役割理解、具体的対応力の強化 |
|
内容 |
・セクハラ・パワハラ定義 |
|
時間 |
3時間 |
|
詳細 |
ハラスメント再発防止のためのオンラインコーチング

ハラスメントに対する基本知識の再確認と、管理職として必要な指導とハラスメントの違いを理解し再発を防止します。複数回に分けて実施します。
|
対象 |
管理職、中堅、経営層 |
|---|---|
|
目的 |
再発防止、指導とハラスメントの線引き理解 |
|
内容 |
・最新ハラスメント基礎知識 |
|
時間 |
全3回(2時間、1.5時間×2) |
|
詳細 |
カスタマーハラスメント対策研修

本研修では、カスタマーハラスメントへの適切な対応力を高め、従業員の心理的負担を軽減し、健全な職場環境の構築を目指します。
|
対象 |
管理者(2次対応者)、1次対応者 |
|---|---|
|
目的 |
カスタマーハラスメント対応力の向上 |
|
内容 |
・カスハラ定義・法律ガイドライン解説 |
|
時間 |
管理者向け2h×2回/1次対応者向け1日 |
|
詳細 |
ハラスメント対策の基礎知識と最近の動向
ハラスメント防止特集まとめ-研修を検討するための知識-
ノビテクでは、過去「ハラスメント防止特集」を公開しました。
山藤祐子 – ハラスメント防止の対策と動向
専門家の山藤祐子氏にその原因と対策、企業研修の現状について聞きました。
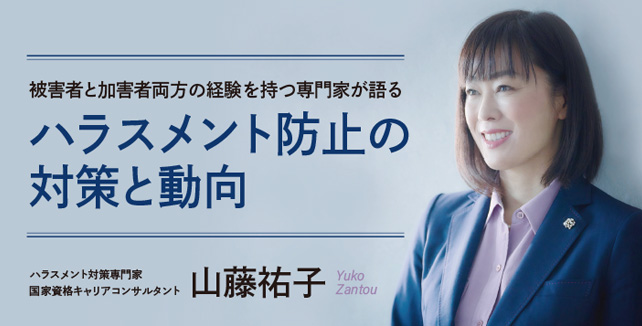
職場に与える影響
- 報連相の機能不全:本音が言えず、意思決定の質も低下。
- 生産性と士気の低下:委縮と萎縮が連鎖し、やる気を失う。
- 人材流出:優秀な人から辞めていく。
「上司が出勤する姿を見るだけで体が硬直する」という声も珍しくない。(山藤祐子)
指導とパワハラの境界
- 判断基準は2つ:業務上の必要性があるか。方法・程度が適切か(✅ ミスを注意 → OK/❌ 侮辱・長時間の叱責 → NG)
- 主なパワハラ行為:暴言・暴行、孤立させる、極端な業務命令、プライバシーの侵害
「なんでもハラスメントになる」と思い込む必要はない。正しい指導は問題ない。(山藤祐子)
加害者になりやすい人の特徴
- 正義感や完璧主義が強すぎる:「こうあるべき」という理想が強く、他人への要求が過剰になる。
- マネジメントの知識不足:部下の叱り方や対話方法を知らない。
- 過去の成功体験への固執:「俺の時代はこうだった」が通用しない現代。
「私も過去、自分がパワハラ上司になっていた。部下が鬼と呼んでいると知っても『売上が全て』と思っていた。」(山藤祐子)
過度に恐れず、コミュニケーションを取る
- 管理職が部下と距離を置きすぎるのも問題。
- 「嫌がられたらハラスメント」ではない。
- 大切なのは状況説明と誠実な対話。
「部下とのコミュニケーションを恐れてはいけない。説明不足が誤解を生む。」(山藤祐子)
最新のハラスメント防止研修の傾向
- 全社員対象が主流:管理職だけでなく、派遣社員・アルバイトも含む全員で知識共有する方向へ。
- 研修テーマの多様化:アンガーマネジメント、アンコンシャス・バイアス、リモハラ対策、ハラスメント対応の初期ヒアリング
- 実践的なケース検討:「これってパワハラ?」を具体例で議論する演習が効果的。
「共通言語ができれば、なんでもハラスメントだと騒ぐ問題は減っていくはず。」(山藤祐子)
初期対応で大事なこと
- 窓口対応者がその場で判断しない:事実と解釈を切り分け、冷静にヒアリング。
- 第三者調査の重要性:同様の被害が他の社員にも及んでいないか確認する。
「泣きながら訴えられると動揺するのは当然。でもその場で『ハラスメントです』と決めつけない。」(山藤祐子)
ハラスメント気質の上司への対応
- 本人は無自覚であるケース多数
- 周囲からのフィードバックが重要:「研修でこの表現はパワハラになると習った」「こういうやり方は今は合わない」と空気感をつくる
「本人だけで変わるのは難しい。周囲が声を上げないといけない。」(山藤祐子)
オンライン時代の課題
- リモート下では他人の目がなく、ハラスメントがエスカレートしやす
- 1on1などマンツーマン面談では、「上司が7割聞く意識を持つ」
「面談内容に関して、第三者によるチェック体制があると安心」(山藤祐子)
まとめ:防止のために必要なこと
- 正しい知識を持つ
- 被害者の感情や立場を理解する
- 過剰に恐れず、誠実にコミュニケーションする
- 全員で共通認識を持つ研修を行う
「まずは知識を学び、そこから行動へ。誰もが安心して働ける職場を作ることが、企業の未来を支える。」(山藤祐子)
貴社のハラスメント対策の一助になれば幸いです。研修のご相談はこちらから。
お問い合わせ
受付時間 平日9:00~18:00
- 研修講師
- アダプティブリーダーシップ
- 女性活躍
- しごとっち
- ロジカルシンキング
- ハラスメント
- コーチング
- AI
- キャリア研修
- 詳細条件から研修を探す
- 課題から研修を探す


